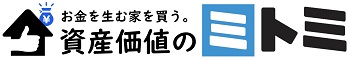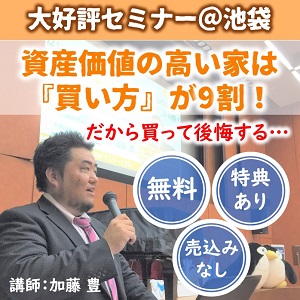住宅予算を引き上げたい…マイホーム購入資金を増やす3つの方法と注意点

住宅資金が足りない!マイホーム購入のためのお金を増やす3つの方法とは
マイホーム探しをしている中、買いたいなと思った物件が当初決めた住宅予算をオーバーしていることはよくあります。
それが10万円程度なら問題ないですが、住宅購入の場合には「予算より300万円多い」といった100万円単位のレベルです。
その時に、あまり深く考えずに「住宅ローンで借りる額を増やそう」とすると後の生活に大きな影響を及ぼすことがあるので要注意です。
ここでは、住宅資金を増やす代表的な方法とやってはいけないことを具体的に見ていきましょう。
目次
①住宅ローンの増額は原則NG。家計改善による余剰資金の範囲内ならOK
設定した住宅予算では欲しい物件が買えない時、住宅ローンの借入額を増やすケースがありますが、おすすめできません。
安易に住宅ローンの返済額を増額すれば、その後の家計を圧迫し、返済に困ってしまうことになりかねないからです。
ローン返済額を毎月1万円増やすことで、約350万円(借入期間35年・金利1%の場合)の予算を増やすことができます。「毎月1万円なら…」と安易に考えてしまいがちです。
しかし、毎月、継続して1万円を多く支払い続けなければならないことは結構大変なことです。お子さまの入学や塾の費用、病気やケガの一時的な出費など長い人生、お金のやりくりが大変な時は何度もあるでしょう。

その家計の波に関係なく、毎月1万円を多く支払い続けることを、今この瞬間で決めてしまうことは慎重になるべきことです。
実際、フラット35で長期固定住宅ローンを貸し出している住宅金融支援機構が公表しているデータによれば、住宅ローン返済が難しくなった人が過去15年平均で「約6.2%」います。つまり、16人に1人の割合で住宅ローンの支払いに困窮しているのです。
その場の雰囲気でなんとなく決めた住宅ローンの増額が将来の生活に暗い陰を落とすことになりかねないのです。
家計改善で住宅資金を増やせるならローン増額もOK!キャッシュフロー表を作ろう
住宅ローンの借入額を増やすことで、当初想定していた物件金額を引き上げることは原則としてNG行為です。
しかし、今現在の家計を見直し、家計状況を合理的に見直すことで余剰資金が生まれるのであれば、それを住宅資金に回しても問題ありません。
ミトミでは、独立系のファイナンシャルプランナー(お金の専門家)を外部からお呼びし、住宅購入予定者の一生涯のキャッシュフロー表を作成します。
住宅購入予定者(お客さん)には普段の生活費の内訳を振り返ってもらいます。その際に、無駄な出費がかなりある場合や、気づいていない支出(使途不明金)など、普段の生活に改善できる余地があるケースがほとんどです。
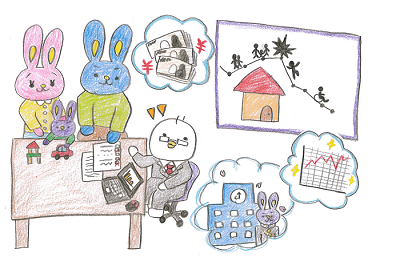
例えば、外食の回数がかなり多い場合、ご本人でも「こんなに外食する必要なんてない。もったいない…」と気づくのです。外食の回数を減らすだけで月1万円以上削減できることもザラです。
そういう費用を負担なく削減していけるのであれば、その浮いた費用を住宅資金に回すことは問題ありません。
問題となるのは、あらかじめ詳細に検討した結果算出した住宅予算を、魅力的な物件があるからといって、あまり深く考えずに後から予算を増やすことです。
一生涯のキャッシュフロー表を作成し、「いくらなら家計に問題ない支払い額か?」「生活改善で生み出せる余剰資金はいくらか?」などを洗い出して、安全な住宅予算を決めてくださいね。
②親や祖父母が住宅資金の贈与をするのはOK。お金を借りるのは要注意
住宅予算を安全に増やすには、親や祖父母(直系尊属)から住宅資金の贈与を受ける方法があります。
もちろん、親や祖父母の財産に余裕があり、贈与してくれる場合に限られますが、これが最も安全な方法といえます。
また、「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」の制度を使うことで、一定額まで非課税で贈与できます。

例えば2021年12月31日までであれば、一般住宅の場合1,000万円・省エネ住宅なら1,500万円(いずれも消費税10%が課された取引)まで贈与税がかかりません。
さらに、暦年贈与の場合の基礎控除額110万円は併用できるため、(相続時精算課税制度を使っていない方は)さらに+110万円の贈与を受けても非課税です。
このように、親や祖父母からの贈与によって住宅資金を受けられれば安全かつお得に住宅予算が増額できます。
尚、非課税となるには、受贈者の年齢や住宅の条件など各種要件があります。また、贈与税の非課税額は変化していく可能性が高いです。最新の状況を国税庁のホームページなどから必ずご確認くださいね。
親からお金を借りるのは住宅ローンの増額と同じNG行為。借り方にも要注意
贈与ではなく、親からお金を借りるという方法もあります。しかし、これは住宅ローンの借入額を増やすことと同じであり、安易に借りることはおすすめできません。
親から借りても返済が必要であることに変わりはありません。
さらに将来相続が発生した際に、他の兄弟(相続人)にこの債権が相続されれば、その兄弟に返済をしていく必要があります。
親は「ある時に返済してくれたらいいよ」と甘えを許してくれても、債権が移動し、厳しい兄弟が債権者となればそうはいかなくなります。
これはあくまで一例ですが、親であってもお金を借りればそれは全額返さなくてはいけないお金です。当たり前ですが返済負担が増えることを理解し、安易にお金を借りることは控えた方が無難でしょう。
尚、親からの借入だからといって、借用書を作らない、無利息、出世払い(返済日を決めずにお金がある時払い)、現金手渡しで返済など、しっかりと返済条件を決めずにあいまいにしがちでもあります。
こういった場合には、税務署の判断で贈与とみなされることもあります。
銀行から借りる時と同様に、返済条件を定め、借用書(金銭消費貸借契約書)を作り、銀行振り込みによる返済(通帳記帳で記録を残す)ことが大事です。
③頭金を増やすのはOK…でもあまり現実的でない。デメリットも大きい
予算の額を上げる手段として、住宅資金(頭金)を貯めるという手もあるでしょう。最も安全で優れた方法といえます。
ただし現実的でないことが多いのも事実なのです。例えば住宅資金(頭金)を300万円増やそうとした場合、何年で貯まるでしょうか。
毎月5万円ずつ貯蓄していくとすれば60カ月(5年間)もかかってしまいます。頑張って10万円ずつ貯蓄していっても、2年半かかります。かなり時間がかかってしまうのです。

マイホーム購入しようと思うタイミングは、結婚を期に夫婦一緒に暮らすためや、子どもの成長によって家が手狭になったことなど、住宅購入を延期することをこれ以上待ってくれない事情がある場合も多いです。
そのような中で数年間、家を買うのを先延ばしにするのは現実的でないことが多いです。
さらにその間、賃貸物件に住んでいる場合には家賃の支払いが発生し続けています。家賃が月10万円であれば、5年間で600万円、2年半で300万円もの支出が発生します。
つまり、毎月家賃を支払ないながら貯蓄していくのであれば、さっさと家を買った方がお得なケースが多いです。家賃支払い分を住宅ローン返済に回した方が無駄がなく、時間も節約できるからです。
自己資金を貯めても、金利上昇や返済期間の短縮で住宅ローンの額が下がるリスク
無事、目標の住宅資金を貯めることができたとします。
その時に、住宅ローン金利が上昇していたり、年齢が45歳を超えて返済期間が最長35年間で組めない場合などには、住宅ローンを組める額(借入可能額)が大きく減らされるリスクがあります。
予算を増やそうと思って数年かけて貯めたのに、逆効果になってしまうという結果ににあることがあるのです。

または、住宅ローンの借入額自体は希望する金額を借りられても、返済期間が短くなれば、毎月の返済額が増加します。結果として家計を圧迫するケースもあるでしょう。
さらには、住宅資金が貯まった時に買いたい希望物件に出会えない可能性ももちろんあります。
結局は、家を買おうと思ってから慌ててお金を貯め始めてもデメリットがかなり大きいのです。
住宅資金を貯めてからマイホームを買うのは、事実上、若いうちから数年間の計画を立てる人や、住宅ローンの借入可能額が物件金額を下回るため自己資金を増やさなければならないケースに限定されるといえるでしょう。
【まとめ】適正予算を決めることが住宅購入の第一歩!FP相談をおすすめ
住宅資金を増やす代表的な方法とその注意点をご紹介しました。
その場の雰囲気で大きな予算引き上げを行うと、将来に悪影響を及ぼすリスクがあります。特に住宅ローンの引き上げは「毎月1万円を我慢すればいいんだから大丈夫だよね」と安易に考えがちですので注意しましょう。
一方で、あまりにも堅実すぎる予算設定では、購入できる物件もできないというジレンマも生じます。
ですので、必要に応じてファイナンシャルプランナーに相談(FP相談)し、物件探しをする「前」に、資産状況に応じて低すぎず高すぎない現実的な予算金額を慎重に検討することをおすすめします。
ミトミでは、住宅購入検討者向けに、第三者の独立系ファイナンシャルプランナー(FP)によるキャッシュフロー表作成を行い、一生涯の家計状況をシミュレーションします。
そこから逆算して、適正な予算を割り出すことで、経済的に安全な住宅購入を実現しています。
「なんとなくイメージで予算を決めてるけど大丈夫かな…」とご心配の場合など、資金面でも詳細な検討をしたい場合にもお気軽にお声がけくださいね!
【P.S.】失敗しない家の買い方を2時間でマスター!【大好評セミナー】
現在「家の買い方セミナー」(無料)を開催中です。
多くの方から高い評価を得ているこのセミナー。まだ家を買うかどうか決まっていない方から、既に取引を進めている方までぜひお気軽にご参加ください!
※【実績】最高評価“来て良かった!”が98%超!